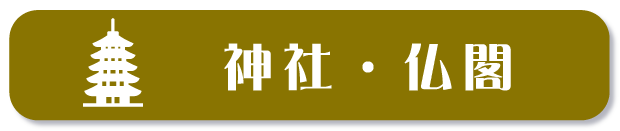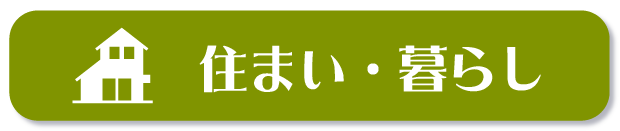金剛山鎮守、楠木家氏神の南河内随一の古社で、かつての戦艦金剛の艦内神社でもありました。
霊峰金剛山の総鎮守で、古来より付近18村の産土神とされ、楠木家の氏神でもある建水分神社(たけみくまりじんじゃ)。「水分神社(すいぶんじんじゃ)」とも呼ばれ、元々は、西暦前92年(崇神天皇5年)、金剛葛城の山麓に水神として奉祀されたのが始まりとされ、1334年(建武元年)、後醍醐天皇の命により、楠木正成公(くすのきまさしげこう)が社殿を現在地に移し、本殿・拝殿・鐘楼等を再営したと伝えられています。
中世の時代には、織田信長の河内国攻略によって社領没収、焼討ちの被害等により、社頭は一時衰退しましたが、豊臣秀吉から寄進を受け、次第に復興して行きました。
本殿は、桧皮葺の三殿が渡廊で連結する全国唯一の様式で、国の重要文化財に登録されています(一般参拝は拝殿まで)。
摂社の「南木神社(なぎじんじゃ)」は、楠木正成公を奉祭する日本最古の神社で、現在の社殿は、1940年(昭和15年)に官幣社建築に準じて建替えられたものになります。
また本社の大鳥居と狛犬は石造で大阪府内最大級です。
末社:金峯神社
また、この神社は上水分社(かみのすいぶんのやしろ)とも称され、美具久留御魂神社(みぐくるみたまじんじゃ<下水分社(しものすいぶんのやしろ)>・富田林市)、錦織神社(にしこおりじんじゃ<中水分社(なかのすいぶんのやしろ)>・富田林市)とともに「河内国の三水分(みくまり)社」と呼ばれています。