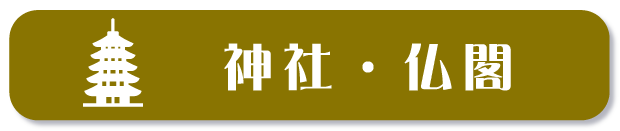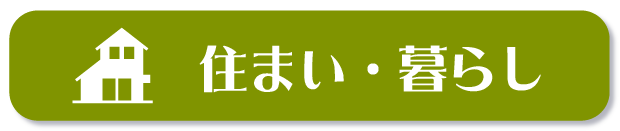元はこの地域には古くから土師氏(後の菅原氏)の祖神の天穂日命(あまのほひのみこと)を祀る「穂日の社(ほひのやしろ)」があったそうで、依羅三宅天満宮(よさみみやけてんまんぐう)と呼ばれていたそうです。
朱雀天皇の時代(平安時代中期)に、釈道賢(しゃくどうけん)という人が参詣した際に十一面観世音のお告げがあり、道賢は現地の住民と協力して、942年(天慶5年)に菅原道真を祭神として創祀され始めました。(屯倉神社が所蔵する『三宅天満宮梅松院縁起』による。)
鎮座地は畠山氏の国人衆である三宅氏の居城跡とも言われています。
当初は、河内国丹比郡依羅三宅天満宮と称していましたが、明治時代の頃より屯倉神社と称するようになったそうです。
御本殿には御神像としてほぼ等身大の菅原道真像が安置されています。
正面鳥居をくぐると鳥居奥には見返り橋と社殿に続く参道があります。
木製朱塗の正面鳥居は、中高野街道に面した境内西端の小字名「馬場先」にあり、「天満宮」の扁額を掲げられています。
◆ 開運松原六社参り
元日・1月1日から1月15日まで開催される正月行事。
松原市と大阪市東住吉区にある6つの神社(松原六社<まつばらろくしゃ>)で行われます。
◆ 梅まつり
境内のたくさんの枝垂れ梅が咲き乱れ、見頃を迎える頃に行われる行事。

その他にも行事が行われており、毎年多くの参拝者が訪れる神社。
そんな随所に歴史を感じられ、多くの方が参拝される屯倉神社にお詣りされてはいかがでしょうか?