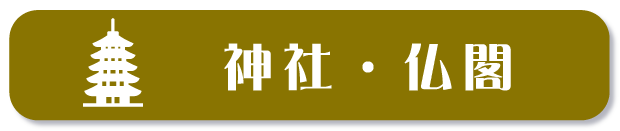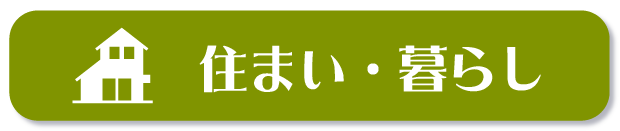誉田八幡宮は、応神天皇を主祭神とし、古くから応神天皇陵(誉田御厨山古墳/こんだみくりやまこふん)の近く(隣)にあって、御陵祭祀を司ってきました。
社伝によると、559年(欽明天皇20年)に応神天皇陵前に神廟が設置されたことをもって創建としており、最古の八幡宮と言われています。
応神天皇の諱(いみな)は、誉田別尊(ほんだわけのみこと)と呼ばれ、現在の羽曳野市誉田にゆかりがあるとされています。天皇が幼少の頃に居住されていたところであり、この地の誉田真若王(こんだまわかのおう/ほんだまわかのおう)の娘、仲津姫(なかつひめ)を皇后にされたと古記に伝えています。
平安時代の永承6年(1051年)には創建の地より1町ほど南にある現在地に遷座し、後冷泉天皇による行幸が行われたそうです。
また、奈良時代には行基によって神宮寺であった長野山護国寺が建立され、本堂はこの南大門の西方正面に位置していたそうです。
大和川や石川の流れる河内地方は、4世紀後半には日本と朝鮮半島と関係の緊張が高まるにつれて、瀬戸内交通の重要性が加わり、一層開発が進んだと考えられます。この機に有力氏族らに支えられた応神天皇は、河内地方を支配して、ここに新王朝を築かれたと考えられています。
秦の始皇帝陵などと共に世界でも屈指の大帝王墓と言われる応神天皇陵や仁徳天皇陵などをはじめ、倭の五王時代の天皇陵はほとんどが、この河内、和泉地方につくられています。
応神天皇の崩御に際して御陵がこの誉田の地に築かれたのは、このように天皇ゆかりの地であったことと、4~5世紀代におけるこの地方(南河内地域)が、重要な位置を占めていた地理的環境によるものであると考えられています。
また、応神天皇の頃は、中国大陸や朝鮮半島からいろいろな文化や技術が導入されて来ました。 中でも当宮に伝わる、応神天皇陵陪塚丸山古墳出土の馬具(金銅製透彫鞍金具)に象徴されるように、当時の金工、木工、革工などの秀れた工芸技術は、後世日本文化の基礎を築くものであったとされています。