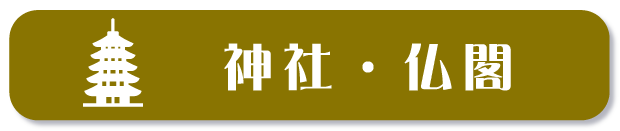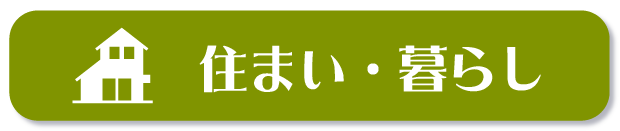古室山古墳(こむろやまこふん)は、国府台地の西側縁辺の自然の地形を利用し、前方部を北東に向けて造られた中型の前方後円墳です。墳丘長150m、前方部幅100m(高さ9.3m)、後円部径96m(高さ15.3m)。
古市古墳群(世界文化遺産)を構成する古墳の1つで、1956年(昭和31年)に国の史跡に指定され、2001(平成13)年に国の史跡として「古市古墳群」に指定されています。
 墳丘は3段に築成され、各段のテラスには円筒埴輪の列がめぐりました。
墳丘は3段に築成され、各段のテラスには円筒埴輪の列がめぐりました。
くびれの両側には造出しが設けられており、周囲には馬蹄形の周濠(現在は埋設保存済み)が巡らされており、墳丘外表では葺石・円筒埴輪列・形象埴輪(家形・盾形・靫形・蓋形・冑形埴輪)が発見されています。
また、墳丘周囲には周濠・周堤が巡らされ、堤内側斜面においても葺石が発見されています。
古墳時代中期の4世紀末-5世紀初頭頃の築造と推定されているそうです。
古市古墳群では最初の大王墓と目される津堂城山古墳(藤井寺市津堂)と同時期とされ、巨大前方後円墳(大王墓)に次ぐ大型前方後円墳として、当時のヤマト王権の政治階層を示す古墳とされています。
墳頂まで登って散策することでき、台地の高所に位置するため眺望がよく、古市古墳群のほかに、玉手山古墳群も遠望できます。
また、季節により梅、桜、紅葉などを楽しむこともできます。
参考:古市古墳群世界文化遺産登録登録推進連絡会議『古市古墳群を歩く』
写真:藤井寺市教育委員会提供