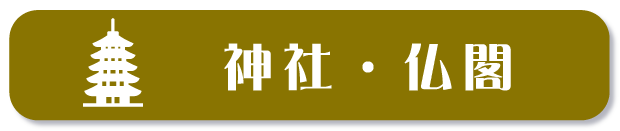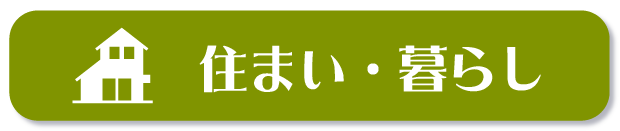寺内町の中心となるお寺。大ヶ塚御坊・八朔寺(はっさくでら)とも呼ばれています。
その歴史は中世の時代に遡り、1573年(元亀3年)に顕如上人によって大ケ塚総道場として開かれ、後にお寺となったそうです。
1795年(寛政6年)に建てられた大屋根の本堂がありましたが焼失し、今の本堂が再建されて今に至るそうです。
御本尊は「阿弥陀如来立像」をまつられています。
毎年9月には、400年以上続く「八朔法要」が執り行われ、「八朔市」で賑わいます。
八朔(八月朔日=8月1日のこと)とは鎌倉初期の時代から農家に伝わる慣習で、一番暇な時期に物の物々交換を行ったと言われており、これを戦乱が収まった天正時代に村人たちと三寺院(顕証寺・大念寺・善正寺)が村の復興を願って大々的に取り組んだ行事のことを指します。
境内には蝋梅や夏水仙、金木犀、彼岸花など、季節折々の草花が植えられており、それぞれの季節を身近に感じることができます。