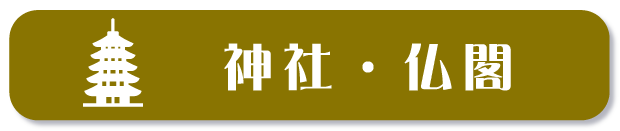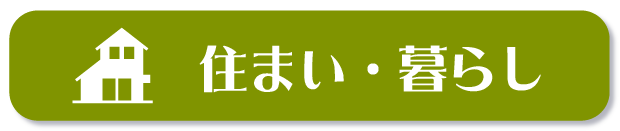西高野街道と並行している古い道、高野山九里道標石の近くにある行者堂で毎年8月に行われる伝統行事で、古野山上講の人たちによって、古くから守り伝えられてきました。
不動明王の縁日である8月28日直前の土曜日に行われ、当日は行者堂の前にお供え物と提灯を飾られ、小さな護摩壇が設けられるそうです。
山伏が法螺貝を吹いて入場し、護摩壇のそばに着席すると、祈祷とともに護摩焚きが始まります。
これに合わせて参列した講の方々が行者堂に参拝されます。
山上講(さんじょうこう)は、かつては市内の村々にあり、役行者/役小角(えんのぎょうじゃ/えんのおづぬ)を祀り、定期的に役行者が開いた山のうち最初に開山され、修験道発祥の「霊峰」として崇められて来た、奈良県にある大峯山(おおみねさん)に登っておられたそうです。
男性中心の組織である山上講は地域の若者が大人の仲間入りをする際の通過儀礼として、大峯山で修行させたと言い伝えられています。
このような風習は次第に廃れてきましたが、古野山上講では、今も2年に一度、大峯山登山を行われているとのこと。
ご興味ある方はぜひ一度訪れてみられてはいかがでしょうか?