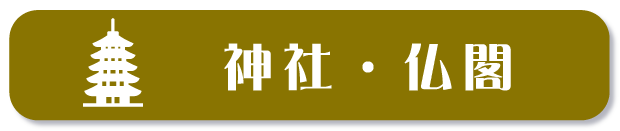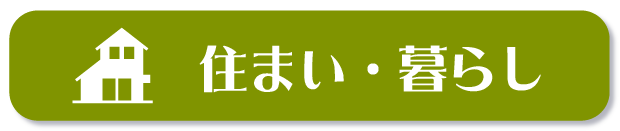八幡神社は、通称:流谷八幡神社とも呼ばれている神社で、石清水八幡宮(京都府)の別院として御神体を勧請し、この地に社殿を造営したことに始まります。
鎌倉時代には社殿の修理が行われ、1340年(延元5年)に八幡神社のために鉄製湯釜が造られていることから、創建時代は古く中世は鎌倉時代より以前だと考えられています。
ちなみに、この湯釜は1340年(延元5年)の銘のある古いもので、1975年(昭和50年)に大阪府の文化財に指定されました。
石清水八幡宮より祭神を勧請したと伝わる日(1月6日)にちなみ、毎年1月6日に近い土曜日か日曜日のいずれかに、神社の氏子らにより対岸の大杉(勧請杉<かんじょうすぎ>)と川をはさんだ柿の木の間にしめ縄をかける『縄掛神事(市指定文化財)』が行われます。
長さ200尺(60m)の注連縄を作り、勧請杉と柿の古木との間に掛ける行事で、1039年(長暦3年)に石清水八幡宮より勧請された際の御柱渡御古例祭で、今も執り行われています。
また、境内には樹齢400年を超えると思われるイチョウの大木があり、こちらは1989年(平成元年)に大阪府の天然記念物に指定されています。