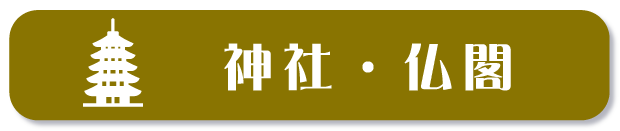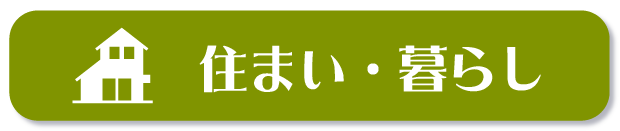創建の由緒は不詳だそうですが、元は二上山(にじょうざん)の上に鎮座していた神社で、「二上権現(にじょうごんげん)」と称されていました。
1238年(暦仁元年<りゃくにんがんねん>)に現在の場所に遷座されました。
現在の場所には元々、恵比須神社(えびすじんじゃ/一名 土祖神社<いちみょう どそじんじゃ>)があり、科長神社がこの場所に遷座するにあたりその末社とされたと伝えられているそうです。
延喜式神名帳(えんぎしきじんみょうちょう/しんめいちょう)には「河内国石川郡 科長神社」と記載され、小社とされているそうです。
江戸時代までは八社大明神と称されていました。
『式内社調査報告』では「藤原頼孝が二上権現を現在の場所に遷座させた時に、藤原氏の祖神である春日神(かすがのかみ)を勧請・合祀し、科長神社の旧名を抑えて八社大明神(はっしゃだいみょうじん)と称したのであろう」と記されています。
また、この地は神功皇后誕生の地と言う伝承もあり、社宝に神功皇后所用と伝える雛形の兜があります。
『式内社調査報告』では「科長→磯長→息長と転じ、息長氏の出である神功皇后の誕生地伝説が生まれたのではないか」と記されています。
1872年(明治5年)4月1日に郷社に定められ、1907年(明治40年)1月28日、神饌幣帛供進社に指定されました。
1907年(明治40年)に近隣の科長岡神社(しながおかじんじゃ)・素盞嗚神社(すさのおじんじゃ)が合祀されました。
境内一帯はかつて飛鳥時代の豪族で、大化の改新で活躍した人物「蘇我倉山田石川麻呂(そがのくらやまだのいしかわのまろ)」の本貫地(ほんがんち)とされており、社頭(しゃとう)には小野妹子(おののいもこ)の墳墓があり、近くには孝徳天皇陵・推古天皇陵があります。
また、太子町内の「磯長山 叡福寺(しながさん えいふくじ)」には磯長陵 (しながりょう、聖徳太子廟所、叡福寺北古墳)があります。
本殿の裏側には八精水と呼ばれる湧き水があり、当麻の刀鍛冶がこの水で刀剣を鍛えたと伝えられています。社宝には神功皇后が使用したと伝える雛形の小さな兜があります。
夏の例祭は神輿と地車(だんじり)を繰り出す祭りで、地車は5つの町会からそれぞれ1台ずつ曳いて、威勢の良いお囃子に合わせて青年団の若者たちが勇壮に曳き回し、神社では三番叟、八社太鼓などの祭事が行われます。
境内社
二上神社
恵比須神社
琴平神社
稲荷神社