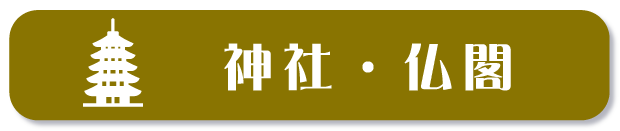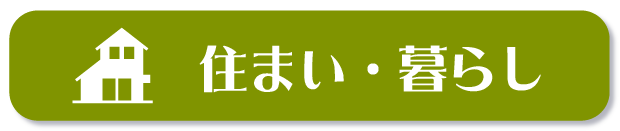江戸時代までは熊野三所権現とよばれ、熊野の神を勧請してできた神社である。
背後には陶器山をひかえ、境内の北方から西方の尾根筋には街道が通る。
明治時代の神仏分離までは境内に金蔵寺があったといわれ、また近くにも光明寺跡、西室院跡、地蔵院跡などの地名が残っていることから、現在の社殿付近から南部丘陵にかけての広い地域に伽藍と鎮守の社地があったと考えられている。
昭和58年の郷土資料館による文化財調査の際に見つかった昆沙門天像は鎌倉時代末期の作であることが判明し、このことからも金蔵寺繁栄の歴史を知ることができる。

参道入り口

文殊地蔵尊

鳥居と手水舎

拝 殿
撮影時が秋祭りのため、提灯が飾られています。
普段は、提灯が無い状態です。
 拝殿側から見下ろした参道
拝殿側から見下ろした参道

拝殿の左側に向かうとご参拝順路と記された立て札があります。

春日社

初辰社

熊野三宝荒神社

稲荷社

稲荷社から先はスズメバチの巣がある様で入れなくなっていました。
 三都戎神社
三都戎神社

三都戎神社側に外からスロープで繋がっているところがありました。

三都神社は秋祭りに地車が5台:隠(かくれ) 、山伏(やまぶし)、山本(やまもと) 、今熊(いまくま)、大野(おおの)宮入します。