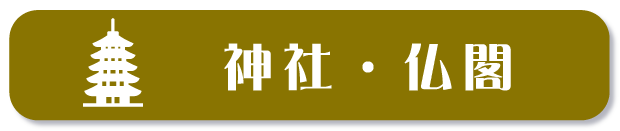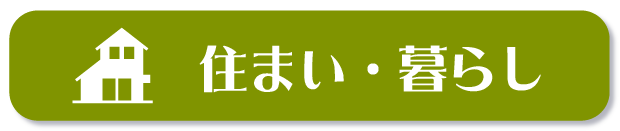寛永18年(1641年)開発の茱萸木新田(くみのきしんでん)の氏神として、観心寺(河内長野市寺元)槙本院(まきもといん)の法印照秀(ほういんしょうしゅう)が勧請した八幡神社が始まりです。
御祭神は八幡大菩薩、愛宕大権現、天照皇大御神、稲荷大明神。
明治末期の三都神社へ合祀するまでの鎮座地は、大野台1丁目の『宮ノ谷』でした。
戦後に『地区内に再び神社を建てよう』との声が高まり、茱萸木中央公民館の敷地に再建します。
昭和60年(1985年)7月29日に竣工式と遷座祭を行い復祀しました。




秋祭りには、茱萸木北(くみのききた)、茱萸木南(くみのきみなみ)の2台のだんじりが宮入します。