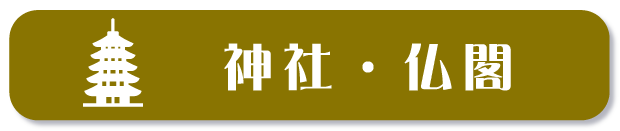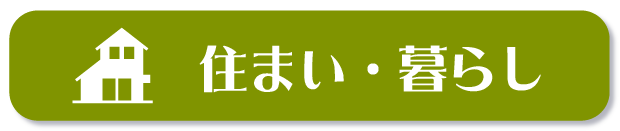元は軽里の西方の伊岐谷にある白鳥陵(軽里大塚古墳)の頂に鎮座し、「伊岐宮」と呼ばれていたそうで、南北朝時代の頃に戦国の兵火により衰微し、峯ヶ塚古墳の頂の小祠として祀られ、1596年(慶長9年)の慶長の大地震で倒壊しましたが、1784年(天明4年)に古市の氏神としてこの地に移され再建されたそうです。
「日本書紀に記された白鳥伝説の聖地」としても知られており、日本書紀には①能褒野(のぼの:現在の三重県亀山市)、②大和琴弾原(ことひきのはら:現在の奈良県御所市冨田)、そして③河内の旧市村 (ふるいちむら:現在の大阪府羽曳野市古市)のこれら3ヶ所が「白鳥伝説の地」として記されているそうです。
その伝説によると、白鳥に姿を変えたヤマトタケルは最後に、河内の旧市村 (ふるいちむら=大阪府羽曳野市古市古市)に降り立ち、その後、天に昇られたとされており、白鳥神社が鎮座する羽曳野市古市は「日本武尊(ヤマトタケル)白鳥伝説・最後の地」ということだそうです。
「羽曳野(はびきの)」と言う地名は、旧古市村(現在の羽曳野市古市の地域)に飛来した日本武尊(やまとたけるのみこと)が、「羽を曳くように再び飛び去った」という話に由来していると伝えられています。
【御祭神】
日本武尊(やまとたけるのみこと)
素戔嗚命(すさのおのみこと)
稲田姫命(くしなだひめのみこと)
【配祀神】
饒速日命(にぎはやひのみこと)
広国押武金日命(ひろくにおしたけかなひのみこと)
【年間行事】
●歳旦祭(さいたんさい)
1月1日に宮中および諸神社で行なわれる祭祀。
新年を祝い国民の福祉、五穀の豊穰、皇室の繁栄を祈るものです。若水をはじめ、御飯・御酒・海・川・山・野の種々の神饌をお供えします。
●節分祭(せつぶんさい)
2月3日斎行。
節分祭は暗く寒かった時期から、木々が芽吹く暖かな春を迎える季節に変わり、罪や穢れを祓う厄除けの行事です。
●夏祭り(なつまつり)
7月11日・12日斎行。
みそぎ浄めて罪やけがれを祓うために行なわれる祭。
陰暦では4月、5月、6月ですが、一般に陽暦5月上旬の立夏から8月上旬の立秋までの祭礼をいいます。
●秋祭り(あきまつり)
10月9日(※本殿での祭典のみ)。
本来,旧暦の7月から9月まで、または立秋から立冬までが秋であり,この期間に行なわれる祭りが秋祭りでしたが、今日では9月から11月頃までに行なわれている祭りを秋祭りと呼びます。
●古市だんじり祭
10月第2土曜日・日曜日斎行。
竹ノ内街道を練り歩き、白鳥神社に六町の地車(だんじり)が宮入します。
この際、境内へ非常に急な坂を一気に駆け上がるところが見どころです。
両日とも多くの屋台が並び、多くの人でにぎわいます。
●伊勢大神楽奉納(いせだかぐらほうのう)
伊勢大神楽は伊勢神宮で古くから行われていた神楽で、舞の起源は古く、飛鳥時代の壬申の乱(672年)にまでさかのぼるほどの歴史のある神楽です。
伊勢神宮のお札を配りながら諸国を巡る神楽で、獅子舞や曲芸などが奉納されます。